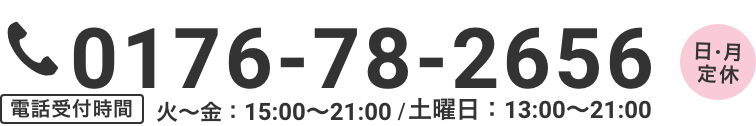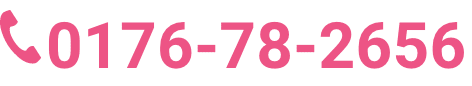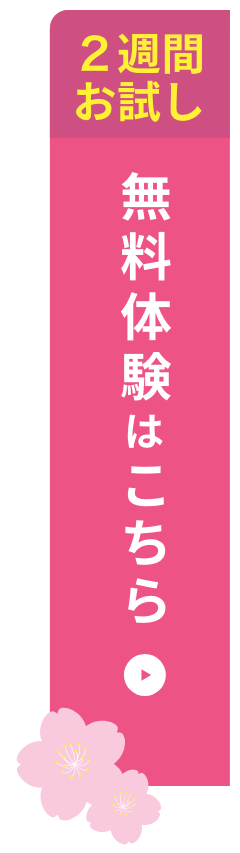志望大学を決める方法
6/29(日)に保護者説明会を実施しました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。
今回の内容はその保護者説明会の一部を抜粋したものです。
ご都合がつかず、不参加だった生徒・保護者様はぜひご覧ください。
~・~・~・~・~・
①大学ってどんな場所?
1. 自分の好きなこと・得意なことを深く学べる場所
小・中・高と、幅広い分野の勉強を全員統一した内容で行ってきたと思いますが、
大学は「1分野に絞って勉強する」ことが基本となります。
2. 同じ夢や価値観を持つ仲間と出会える場所
同じ分野に興味をもった学生が集まるので、
より自分の価値観に近い仲間と出会える確率が増えます。
3. 時間をどう使うか、何に挑戦するかを自分で選べる場所
大学生は自由な時間が多くあります。
その時間を何に使うかは自己責任です。
4. 「将来の自分」をじっくり考え、形にしていく場所
大学では社会に出て戦っていく上での
自分の武器を考え、磨いていきます。
大学で学ぶ専門分野はその1つです。
このように、大学生には「自立」が求められます。
大学を選ぶということは
この「自立」への第一歩。
「自分の人生を、自分で選び始めること」
なのです!
~・~・~・~・~・
②志望学部の決め方
STEP1 興味・関心から考える
◆学校の授業で面白かった科目は?
例:生物が好き → 生命科学、農学、薬学 など
◆普段どんなことを調べたり考えたりしている?
例:ニュースをよく見る → 政治学、経済学、法学 など
◆将来こんなことがしたい!という夢や目標は?
例:子どもに関わりたい → 教育学、心理学、保育学 など
→ 興味のあるキーワードを10個書き出してみよう!
STEP2 将来の進路から考える
◆なりたい職業がある人
→ それに必要な資格・知識から学部を調べる
例:臨床検査技師 → 医療技術系学部
さて、STEP1と2で決められれば理想ですが
これができないから志望学部が決められないという
生徒が多いことでしょう。
そこで次のSTEP3と4を試してみてください。
STEP3 学部で学べることを調べる
◆どんな学部があるかを知ろう!
◆それぞれの学部ではどんなことが学べるかを知ろう
→ 大学のHP、YouTubeなど
↑ちょっと重たいかもしれません
YouTubeの例は他塾さんの動画が多いのでリンクを控えます!笑
◆足を使っていろいろな体験・情報収集をしてみよう
→ オープンキャンパスへ行く、卒業生の話を聞く
高3の夏に受験勉強に専念するために、
オープンキャンパスはぜひ高1・2生の時に行っておきましょう。
決められない理由は「知識不足」のことが多いです。
まずは知識を入れる努力をしてみましょう。
新しい発見があるはずです。
STEP4 それでも決められない場合
◆就職先が幅広い学部を選ぶ(文系)
→ 経済・商・法学部など
◆「今後伸びそうな業界」や「無くならない業界」から選ぶ(理系)
→ 情報系、機械系・電気電子系など
◆消去法(やりたくないことを選択肢から外す)
→ × 人との関わりが多い、× 屋外で働く仕事は嫌だ
消去法は結構おすすめです。お試しあれ。
~・~・~・~・~・
③志望大学の決め方
理想的には大学のHPやパンフレットを見て
「この大学が良い!」と決められたら良いですが
なかなか現実は甘くないです。
現実的な志望校の選び方をお伝えします。
要素1 偏差値
個人的には出来るだけ高い偏差値の大学に入ることをお勧めします。
①就職活動で有利に働くことがあるため
②モチベーションが高い学生が多いため
→自分のモチベーションアップにもつながるかも
この2つの理由からです。
要素2 立地
「東北が良い」「暑い地域は嫌だ」「都会が良い」など
要素3 学費
できれば国公立へ行ってほしい!など
要素4 受験科目
「数学Ⅰ・Aだけで受けられる」「理科が二次試験でいらない」など
学部の方向性が決まると、志望大学はスムーズに決まる場合が多いです。
~・~・~・~・~・
いかがだったでしょうか。
「志望校が決まらないから勉強できない」と言っているそこの君!
まずは大学の知識を取り入れる努力をしてみよう。
自分の人生を自分で決めることはとても大変です。
でも、大人になったらずっとその繰り返しです。
「自分で志望校を決める」ということは
自立への1歩であると冒頭でお伝えしました。
私の考えで恐縮ですが
自分で志望校を決めることは一種の親孝行だとも思います。
生徒にはぜひしっかり調べて
納得のいく志望校を決めてほしいと思います。